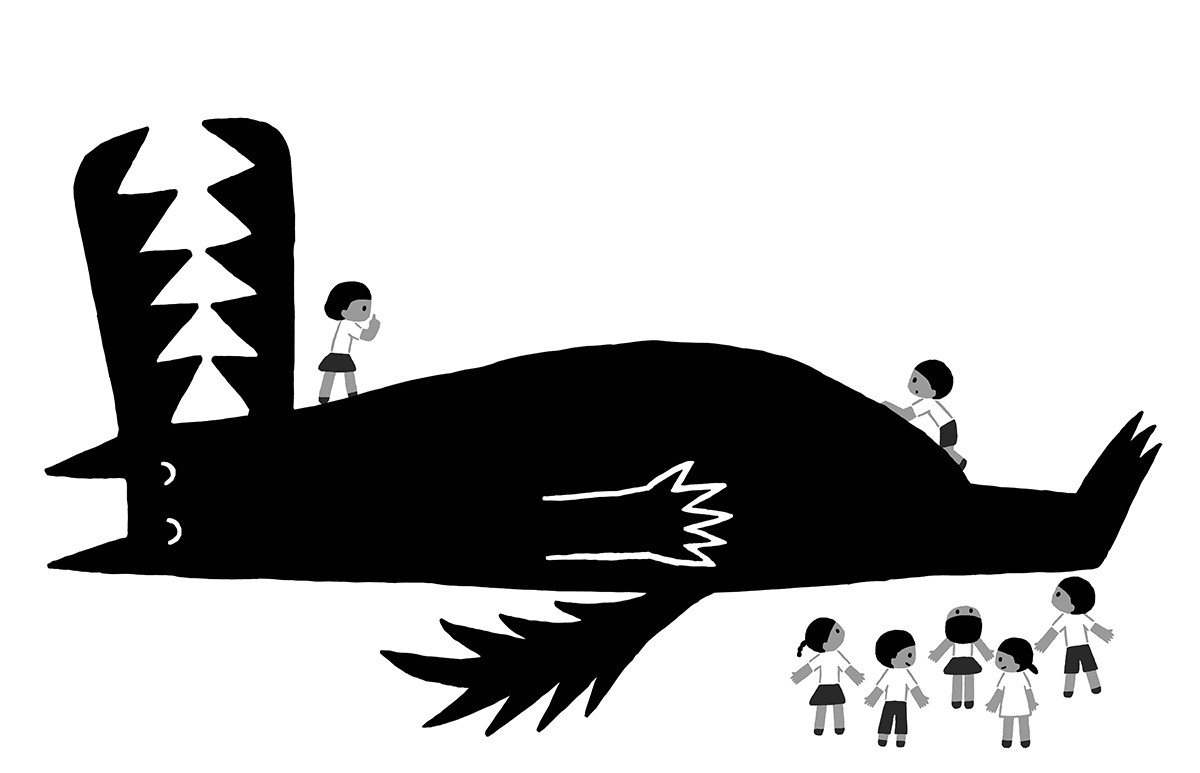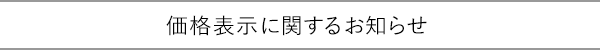胸を疼かせる、幼い少女の特別な夏の体験 映画『悲しみに、こんにちは』 カルラ・シモン監督インタビュー。
自身が初めて生と死に触れた幼少期の出来事を元に、無邪気さと繊細さをあわせ持つ幼い少女特有の心の動きを、カタルーニャの夏の美しい風景を舞台に描いた映画『悲しみに、こんにちは』。誰もが心の片隅に持っている記憶を喚起させ、共感とともに世界に対する新鮮な気づきを与える本作は、子どもにとっての家族や愛の大切さを改めて教えてくれる。
監督は、これが長編デビュー作となるカルラ・シモン監督。

──この映画は、ある子どもが直面したパーソナルな出来事を扱っていながら、観る者の記憶を喚起させ、家族の愛の大切さを伝える普遍的な物語になっています。特にわかりやすく状況を説明してないところが良かったと思います。
「ありがとうございます。おっしゃるように「説明をしない」というのが私がこだわったポイントでした。情報でいっぱいにしてしまわずに、「これはどういう家族なんだろう? 何が起きたんだろう?」と、観客にゲームのように徐々に発見していってもらうように、脚本の段階から考えていました。というのも、現実の世界では、私たちはまわりで何が起きているのか説明を受けて理解していくのではなく、観察しながら少しずつ理解していきますよね。それを映画にも反映しています。」
──そのせいでドキュメンタリーのように見えるシーンもありますが、実は緻密に計算されているんですね。
「実際の脚本は非常に時間をかけて作りましたが、映画にする段階ではそう見えないように、自然なトーンにするのが撮影で大変だったところです。子どもたちには脚本を与えずに、大人の俳優たちにも台詞を全部覚えてもらわないようにして、シーンの中心のテーマは脚本に即していながらも、自分自身の言葉で話してもらうようにしました。もちろん言ってもらわければいけない台詞は子供たちにも伝えて言ってもらいましたが。」

──やはり、最初の長編ではご自身の体験を語りたいという思いは強くあったのでしょうか。
「そうですね。その前に作った「LIPSTICK」という短編が、2人の男の子がおばあさんの死に直面するというテーマだったんですが、それを作り終えたときに、子どもが「死」に直面するというテーマをもっと深めたいと思ったんですね。それならやはり自分の実体験を映画にするのが一番伝わるのではないかと考えたんです。映画学校で勉強していたときに、先生が「自分の知っている世界を描いたほうが伝わる」と教えてくれたのも、頭にありました。ただ、これが普遍的な物語かどうかは、それほど自分では自身がなかったのですが、「これは家族の普遍的な物語だから、観客に気に入ってもらえると思うよ」とプロデューサーに後押ししてもらい、撮ることに決めました。」
──実際に映画を完成したことで、ご自身の中で何か変化はありましたか?
「多くの人に、「この映画があなたの気持ちを浄化する役を果たしたのではないですか?」とよく聞かれたんですが、私としてはすでにこのときの気持ちというのは乗り越えていたので、浄化の意味もその必要もありませんでした。ただ、自分の子ども時代の話は映画にする前からいろんな人に話してきたので、自分の中で一種の「物語」のようになってしまっていたんですが、映画にすることで改めて自分に起きたことを見つめ直す機会になりました。同時に、当時の私の気持ちよりも、特に周囲の人たち、両親や妹がどんな気持ちだったかということがよく分かるようになりました。」
──たしかに、フリダだけでなく、受け入れる家族や周囲の人たちのこともよく描かれていることで、誰が見ても何かしら自分に引きつけて感じることがきるのかもしれません。
「もちろん、最初に撮り始めたときには、自分が上手に伝えることができるのはフリダの視点だと確信をもっていました。ただ撮影していくうちに、撮影監督や編集の責任者などとも話しながら、やはり周囲の人の気持ちも大事だということになり、フリダを受け入れる側の人たちの複雑な心境を伝える場面もとても重要になりました。とはいえ、私にとってこの映画で一番重要だったのは、子どもの心理の複雑さを示すことでした。子どもというのは大人たちが思っている以上に頭が良く、いろいろな状況にも対応し、新しい環境にも適応することができる。そういう能力は誰もが持っていると思うんですね。ただ、適応能力があっても、子どもはその感情を表現することができないので、怒りだったり歪んだ形で外に出てしまうんです。」

──フリダのほうが年上でお姉さんなのに、妹になるアナの方が田舎暮らしに慣れていて、姉妹の立場が逆転してフリダが怒る場面も面白かったです。
「そうですね、都会と田舎のコントラストというのは実際に私が経験したことでした。私はバルセロナのいわゆる都会育ちだったので、田舎の自然は詩的で美しいと思いつつも怖かったというか、脅威でもありました。でも妹はその環境に慣れていましたから、私があとから追いかけていく身分だったんですね(笑)。実際にのフリダを演じたライラも都会育ちの子で、アナ役のパウラは田舎に慣れている子でしたから、実際にその違いを映画の中でも示すことができたのではないかと思います。」
──他にも、フランコ政権崩壊後の自由を謳歌したフリダの母親の世代、その上のおばあさんたちのカトリックの信仰が厚い世代、といった世代間の価値観の差も垣間見えるシーンが印象的でした。
「全くそのとおりで、私自身、何でこんなに保守的でカトリックで、フランコ政権に反対とは言っていなかった祖父母のような人から、私の母のような全く逆の、左派で無宗教な人間が生まれてきたのか、まったく不思議なんです(笑)。でも、それはやはり時代の産物であって、両親はフランコ死後の民主化の時代に若者として生き、『完全なる自由』というものにとても価値を認めた世代だったんです。」
──同じ世代でも新しく両親になる叔父夫婦は、自ら選択して都会から田舎へ移り住みます。そのことは、聴いているジャズなどの音楽からもうかがえました。
「都会育ちの若者が生活のオプションとして田舎暮らしを選んだということで、私の新しい両親は、やはり外から来た者ということをコミュニティの中で感じていたと思います。そのジャズというのは、実際の私の新しい父が趣味でベースを弾いてたんですね。実は、映画の舞台になっている1993年のあとに生まれた弟がもう一人いるんですが、彼は父の影響でジャズをやっていて、この映画のサウンドトラックは彼が作ったんです。ちなみに、妹は女優をしていて、この映画にも出てもらいました。私の映画で兄弟全員が参加することができたのは嬉しかったですね。」
──それはとても素晴らしいですね。
「この映画を作るにあたって、それまで今まであまり考えたことなかった教育ということを、とても考えました。私の今の母親は、この映画で描いた時期というのは、現在の私よりも年齢的にはずっと若かったんです。もし今の私にこんなことが起こったらと考えると本当に大変だと思いますが、そういう状況で、母は子どもたちのことを何よりも優先して、私も妹もその後生まれる弟も、多くの時間と労力を割いて愛情を注いでくれました。そのおかげで、私はとても健全に育つことができたと感謝しています。」

──お話うかがっていても、そのことは充分に伝わります。家族とは何かということを、この映画は改めて観客に提示していますね。
「そう思います。家族愛というのは、どんな子どもでも、健全に育つためには必要なものです。特にフリダの場合は母親を失ったばかりですから、代わりの愛となるもの、家族の愛というものは緊急に必要でした。それがなければ前に進めなかったと思います。」
![胸を疼かせる、幼い少女の特別な夏の体験 映画『悲しみに、こんにちは』 カルラ・シモン監督インタビュー。 | Fasu [ファス]](https://fasu.jp/wp-content/themes/fasu/images/logo.svg)
![胸を疼かせる、幼い少女の特別な夏の体験 映画『悲しみに、こんにちは』 カルラ・シモン監督インタビュー。 | Fasu [ファス]](https://fasu.jp/wp-content/themes/fasu/images/logo_sp.svg)

![Fasu [ファス]](https://fasu.jp/wp-content/themes/fasu/images/logo_white.svg)